| |
|
 |
| 「和食」の一言で括られがちな和の味わい…。 実際は地域によって異なる奥深いものです。 |
|
 |

|
|
|

|
 |
|
|
 |

|
|
|
| |
| 今日はだしがよく効いた薄味の大阪風、明日はコクのある加賀風――。 本場の味の違いを知れば、たとえば煮物一つにしても、その日の気分で味付けを変えることができ和食のバリエーションがぐんと広がります。 ここではそんな楽しみにつながる、各地の味のポイントをご紹介。 『膳』ならではのヒントで秋の食卓をより美味しくしてみましょう。 |
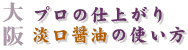 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
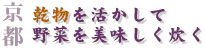 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
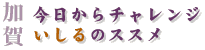 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||

|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||
| Copyright (C) 2002 AHJIKAN CO., LTD. | ||||
 一般の濃口醤油より塩分が2%ほど強い大阪の淡口醤油。その名の通り色が淡く、味にクセがないので、素材やだしの旨み・香り・色を損ないません。上手に使うと料理がプロっぽく仕上がります。
一般の濃口醤油より塩分が2%ほど強い大阪の淡口醤油。その名の通り色が淡く、味にクセがないので、素材やだしの旨み・香り・色を損ないません。上手に使うと料理がプロっぽく仕上がります。 身欠きにしん・干しだらといった塩干魚介(えんかんぎょかい)、湯葉・大豆等の乾物をだし代りにして野菜と炊くのが京都流です。乾物独特の塩味や旨みが野菜にしっとりなじみ、昆布や鰹節のだしとはまた違う、深い滋味と出会えます。
身欠きにしん・干しだらといった塩干魚介(えんかんぎょかい)、湯葉・大豆等の乾物をだし代りにして野菜と炊くのが京都流です。乾物独特の塩味や旨みが野菜にしっとりなじみ、昆布や鰹節のだしとはまた違う、深い滋味と出会えます。 和食を越えたアジア的な味覚を秘めた「いしる」。煮物・鍋物・おでん・麺類のだしをはじめ、炒め物・焼き物・漬け物の調味料、さらに刺身の醤油がわり等、多彩な利用法が魅力です。
和食を越えたアジア的な味覚を秘めた「いしる」。煮物・鍋物・おでん・麺類のだしをはじめ、炒め物・焼き物・漬け物の調味料、さらに刺身の醤油がわり等、多彩な利用法が魅力です。