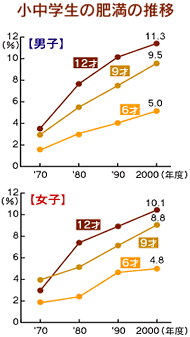「玄米は体にいい」。このところ、そんな話題をよく耳にします。
「玄米」とはそもそも、「モミ殻を取っただけの、精白していない米」のことです。胚芽とヌカがそのまま残り、水につければ芽を出す「生きた米」です。
単に精白の度合いを示し、特定の品種を指すわけではないので、コシヒカリの玄米もあれば、ヒトメボレやアキタコマチの玄米等、いろいろあります。
これに対しておなじみの白米は、精白によって胚芽とヌカが取り除かれているため、水につけても芽は出ません。放置すればやがて腐敗してしまいます。
玄米を食べるとはつまり「生きている植物のタネを食べること」と同じ。ごはん茶碗1杯の中の約3000粒の生命力を、すべて体内に取り込むことなのです。
命を蓄えた米と、そうでない米。同じ米ではあるものの、玄米と白米は根本的に異なるのです。 |
 |
 |
 |
 |
玄米の生命力とはズバリ、豊富な食物繊維とビタミン類、そしてミネラルです。お気付きのように、白米では除去される胚芽とヌカに、健康パワーの大部分が含まれています。昔から「おかずいらず」と言われる玄米は、栄養学的に見てもほぼ完璧。玄米だけ食べていても、栄養バランスが十分に保てるとの説もあります。
精米技術の進歩で、江戸時代後期から白米が市場に出回るようになりましたが、庶民が主に口にしたのは廉価な玄米です。玄米ごはんに味噌汁、焼き魚、野菜の煮物、漬け物という質素な「一汁三菜」が食の基本でした。それでもガンや糖尿病、心臓・脳疾患等、現代で言う生活習慣病に罹る人はごくまれ。生活習慣病に悩むアメリカが「理想の健康食は元禄時代以前の日本食である」と『マクガバンレポート(※)』('77年)で発表するほど、玄米は健康づくりに優れています。
味覚的にも白米より香ばしく、食べ応えのある玄米。初めての方はぜひ挑戦して、今よりもっと丈夫な体を作りましょう。
(※)マクガバンレポート
米国の上院特別委員会が全世界の医学・栄養学者を集めて調査・研究した「食事と慢性疾患の関係」に関する報告書。心臓病やガン等の主原因は肉食中心の生活にあるとし、それらを防ぐ理想食は「精白しない殻類(玄米等)・季節の野菜・小魚を主とした日本の伝統食である」と発表しています。
|
|





 【栄養が燃えず脂肪に】
【栄養が燃えず脂肪に】







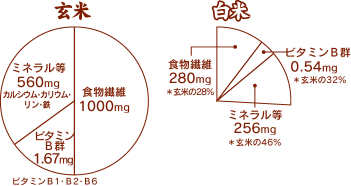
 ●炊飯器
●炊飯器 水の量は白米の1.2倍。フタをして強火にかけ、圧力がかかったら(ピンが上がる、または、おもりが回る)、弱火にして約20分炊き、火を止めます。後は約15分蒸らせば出来上がりです。
水の量は白米の1.2倍。フタをして強火にかけ、圧力がかかったら(ピンが上がる、または、おもりが回る)、弱火にして約20分炊き、火を止めます。後は約15分蒸らせば出来上がりです。 水の量は白米の1.5〜2倍。塩を少量入れて1時間以上浸けておきます。フタをして強火で炊き始め、沸騰したら弱火にして約50分炊きます。この間、フタが動かないよう、重しをしておきます。炊き上がったら、約15分蒸らします。
水の量は白米の1.5〜2倍。塩を少量入れて1時間以上浸けておきます。フタをして強火で炊き始め、沸騰したら弱火にして約50分炊きます。この間、フタが動かないよう、重しをしておきます。炊き上がったら、約15分蒸らします。 調味料は玄米の健康パワーを強める上でとても重要です。特に醤油と味噌は丸大豆を用いた天然醸造の本格派を。無添加の本物の調味料は腸内を有益な菌で満たし玄米の働きを助けます。
調味料は玄米の健康パワーを強める上でとても重要です。特に醤油と味噌は丸大豆を用いた天然醸造の本格派を。無添加の本物の調味料は腸内を有益な菌で満たし玄米の働きを助けます。