| |
|
 |
|
|
|
|
| |
| 食べ物にはすべて陰陽があります。 それぞれの働きを知って、バランスの良い食生活を心がけましょう。 |
|
|
|
|
| |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |
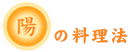
|

|
|
|
| |
| 陰陽のバランスを保ち、健康な体をつくってくれる全体食。 人気野菜のダイコンで「丸ごと味わう」を始めましょう! |
|
|
|||||
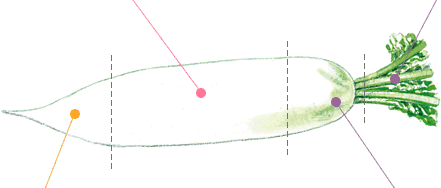 |
|
|
|||||
| ダイコンそのものは、ほぼ中庸の食べ物ですが、部分でみると、陰性に傾くところや陽性の強いところ等に分かれます。全体をまんべんなく食べてこそ、理想的な中庸が保たれる、と言えるでしょう。 普段食べない皮や先っぽも今日からは捨てずに。ダイコンに限らず、土から身を守る皮や栄養を吸収する先っぽ(根)は植物にとって重要な器官です。それだけにしっかり組成されていて、栄養学的にも優れた効果があるのです。部分ごとに料理法を工夫して、すべてを美味しく味わってください。 |
|
|
|
||||
| Copyright (C) 2002 AHJIKAN CO., LTD. | ||||
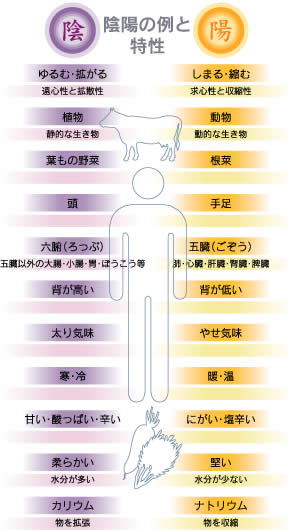






 ●キャベツの芯[陽]・外葉[陰]
●キャベツの芯[陽]・外葉[陰]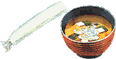 ●ネギの根っこ[陽]
●ネギの根っこ[陽] ●ニンジンの皮[やや陰]
●ニンジンの皮[やや陰]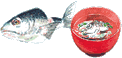 ●魚のアラ[頭暠やや陰][尾・ヒレ・エラ暠
陽]
●魚のアラ[頭暠やや陰][尾・ヒレ・エラ暠
陽]