 |
 |
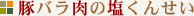 |
 |
 |
 |
| ■材料(豚バラ肉1本分) |
 |
| 粗塩 |
 |
2〜3kg |
豚バラ肉
(かたまり) |
|
1本(約500g) |
| セロリの葉 |
|
2束分 |
| 白ネギ |
|
適宜 |
|
| ■作り方 |
 |
| 1. |
中華鍋に底が見えなくなるくらいの塩を敷き、セロリの葉で包んだ豚バラ肉のかたまりをのせる。 |
| 2. |
1.を塩で覆い、ふた(もしくはアルミホイルで覆う)をして弱い中火で約1時間じっくり焼く。塩がきつね色になったら火を止めてそのまま余熱で火を通す。 |
| 3. |
竹串をさし、スッと通ればできあがり。塩から取り出してセロリの葉を取り除き、スライスする。皿に盛り、白髪ネギを散らす。 |
|
| ※お好みで変わり塩の山椒塩をつけていただいても風味が増し、おいしくいただけます。 |
 |
| 「塩釜風」に料理する贅沢な逸品です。肉と脂が混在するバラ肉の旨みを自然塩が素直に引き出し、惣菜はもちろん、酒肴や麺の具など、幅広く使えます。肉料理には特に岩塩が合うのでお試しを。 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| ■材料(4人分) |
 |
| 【薬味】 |
|
|
| [山椒塩] |
自然塩 |
小さじ3 |
| 花山椒 |
小さじ1/2 |
 |
| [七味塩] |
自然塩 |
小さじ3 |
| 七味 |
小さじ1/2 |
 |
| [抹茶塩] |
自然塩 |
小さじ3 |
| 抹茶 |
小さじ1/2 |
 |
| 【天ぷら】 |
|
|
| ●野菜(しし唐、椎茸、人参などお好みで) |
適宜 |
| エビ |
4尾 |
| [衣] |
小麦粉(薄力粉) |
1カップ |
| 卵 |
1個 |
| 冷水 |
1カップ |
 |
| ●鶏ササミ |
 |
2本 |
| [衣] |
片栗粉 |
 |
適宜 |
| 卵白 |
 |
適宜 |
| 道明寺粉 |
 |
適宜 |
|
 |
| ●白身魚 |
 |
4切 |
| [衣] |
片栗粉 |
 |
適宜 |
| 卵白 |
 |
適宜 |
春雨またはみじん粉
(白・黄色・緑・ピンク) |
 |
適宜 |
|
|
 |
| ■作り方 |
 |
| 1. |
塩はしっとりしている場合はフライパンで炒り、それぞれ花山椒・七味・抹茶と混ぜ合わせる。 |
| 2. |
野菜は食べやすい大きさに切る。鶏ササミは筋を取り、一口大のそぎ切りにし、白身魚も同様にそぎ切りにする。 |
| 3. |
小麦粉・卵・冷水を混ぜて天ぷら衣を作る。春雨は、はさみで1cmの長さに切る。みじん粉は混ぜ合わせておく。 |
| 4. |
野菜、エビは天ぷら衣をつけて揚げ、鶏ササミ・白身魚は片栗粉をまぶしてから卵白を塗り、鶏ササミは道明寺粉、白身魚は春雨またはみじん粉をつけて揚げる。 |
| 5. |
1.をつけていただく。 |
|
 |
| ほのかな旨みや甘味のある自然塩は天ぷらやフライ、串焼きなどの「付け塩」にしても美味しく食べられます。山椒塩、抹茶塩、七味塩と幾つか用意すれば味も風味も変ってアクセントになります。 |
 |



