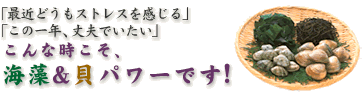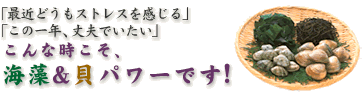冷たかった冬の海が春の陽射しにぬるむ頃、海藻と貝が旬を迎えます。周りを海に囲まれたわが国では古代から海藻と貝が豊富にとれ(※1)、貴重な栄養源となっていました。奈良・平安時代にはこれらを租税として納めていた記録があり、『万葉集』にも海藻や貝を詠んだ歌が残っています。もっとも当時は貴族しか食べられない高価な食べ物(※2)でした。
海藻と貝が庶民の口に入るようになったのは江戸時代から。各藩が漁業をはじめ、
産業奨励に力を入れたことで、海苔やワカメ、ハマグリ、アサリといった幸が広く一般に出回るようになりました。
当時の料理本、『料理物語』や『江戸料理集』にも海藻と貝は人気食材として登場します。たとえばワカメの吸物や味噌汁、醤油味の酢の物、ホタテの焼き物ほか、現代でもおなじみの料理が数多く紹介されています。貝を酒で煎って塩で味付けし、煮たヒジキと合わせる料理等、海藻と貝の相性の良さ(※3)もすでに説かれていて、大変興味深いものがあります。 |
 |
 |
 |
 |
 |
海で育まれる海藻と貝には海水の中のさまざまなミネラル分がたっぷりと含まれています。ミネラルがもたらす「健康パワー」と「味の良さ」を古人は経験として感じ取り、時を超えて語り継いできたのです。中でも「カルシウム」は両者に共通して蓄えられるミネラルです。カルシウムといえば、骨を形作る栄養素と思いがちですが、それだけではありません。実は「精神の安定」にも深く関係し、不安やいらだち、怒りといったマイナスの感情を鎮めてくれるのです。
折しも春は人事異動や新入学、転居等、新生活が始まる季節。環境の変化によるストレスで精神が不安定になり、ひいては体調不良に陥る人も少なくありません。海藻と貝は、そんなストレスをやわらげて元気を保つ、まさに「癒しの恵み」なのです。
また最近は諸々の生活習慣病を予防する健康成分、海藻の「フコイダン」や貝の「タウリン」にも注目が集まっています。健康面が何かと心配なこの時期。海藻と貝で丈夫な体を作りましょう。
(※1)海藻と貝が豊富にとれ:海藻は日本近海に約1,200種が生育。うち食用は、一般市場には出回らず採取地で消費されるものも含めると約100種あります。貝は約5,000種が生息し、うち50種ほどが食用とされています。
(※2)食べ物:奈良・平安時代、海藻はゆでて酢と和えたり、汁に入れて食べていたと思われます。貝は生食をはじめ、焼き物や蒸し物、くんせい、干し物にして食べていたようです。
(※3)相性の良さ:「ワカメとアサリ、赤貝の酢味噌和え」「「アワビの刺身と生の海藻」等が美味しい取り合わせとして紹介されています。 |
|