|
|

|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
食の楽しみを広げる香味・辛味の魅力 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ほんの少し添えるだけで、 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
多彩な薬味の世界 |
|
|
|
すぐに役立つ薬味ファイル |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
「薬味」という言葉は中国から渡来しました。もともとは薬用となる食材が持つ「甘・苦・酸・辛・塩辛い」の5つの味の総称だったのです。それが次第に薬用食材そのものを指す言葉となり、室町時代には、日本で一般に手に入る薬用食材が生姜だったため、生姜が薬味と呼ばれるようになりました。そして、生姜は辛いものの代表であったので、いつしか「辛くて香りの強い食材」を薬味と称するようになりました。 |
料理の味や香りがいま一つ物足りない…そう感じたら、このページを見てください。和食に欠かせない代表的な薬味をまとめました。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
海の幸のいっぱい入ったお鍋。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
七味唐辛子の七味って? |
|
|
薬味の意外な活用法 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
薬味の中には、意外な用途に驚かされるものがあります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Copyright (C) 1999 AHJIKAN CO., LTD.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 おろし:刺身、寿司、ざるそば、冷やしうどん、カブラ蒸し(おろしたカブと白身魚の蒸し物にあんをかけた料理)、うざく(ウナギ蒲焼とキュウリの酢の物)等。
おろし:刺身、寿司、ざるそば、冷やしうどん、カブラ蒸し(おろしたカブと白身魚の蒸し物にあんをかけた料理)、うざく(ウナギ蒲焼とキュウリの酢の物)等。
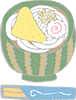 麺類や丼物に付き物の七味唐辛子。この七味とは何でしょう?
麺類や丼物に付き物の七味唐辛子。この七味とは何でしょう?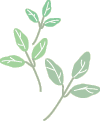 命がけの薬草探し
命がけの薬草探し